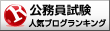公務員試験の教養科目「資料解釈」の勉強方法について紹介します。
資料解釈は、出題数が1問程度とかなり少なく、勉強に時間を使うべきか迷うところです。引っ掛け的な問題が多いので、1周くらいは問題集をやっておくといいかもしれません。
「資料解釈」の勉強で使用した教材
私が使っていた教材は以下の1冊です。
これは、問題集です。
Level1~4の難易度別で問題が載っており、Basicが15問、Standard1が15問、Standard2が15問、Highが15問の合計60問。各問題毎に、その問題を解く目標時間が表示されており、問題演習をする上で目安になります。
また、巻末には計算テクニック集と計算スピードを上げるための練習問題もあります。解説も分かりやすいので、使いやすい問題集だと思います。
私はLevel1~3のBasicとStandardレベルの問題のみで国家1種の問題が多いHighレベル問題は解きませんでしたが、地方上級レベルだと十分だったように感じます。
「資料解釈」の勉強の進め方
私は資料解釈について、出題数が少なく、時間帯効果が低いと感じたので、勉強計画に組み込んでいません。
対策として行った事といえば、教材である「畑中敦子の資料解釈の最前線!」の問題集を、1周程度サラッと問題演習する程度です。
これ以外は、何も行っていません。そのため、かなりぶっつけ本番だったと思います(笑)
「資料解釈」の勉強で難しく感じた点、重要だと感じた点
資料解釈は「面倒」且つ「紛らわしい」問題
この資料解釈で出題される問題は、簡単に言えば「面倒」且つ「紛らわしい」問題です。
経済学のように複雑な計算は不要で、計算も簡単です。そのため、時間さえあれば、かなり確実に正解できる問題だと思います。
しかし、正解の選択肢を導き出すための計算が非常に面倒。
「100+25=125」などの正確な数値を導き出す計算ではなく、「135×294は4万より小さい」というような、ざっくりとした計算です。
暗算が得意な人や、効率よい計算方法を知っている人なら問題ないと思いますが、私は暗算などの計算が苦手なので、1つの選択肢を正解かどうか計算するだけで、すごく時間がかかります。
そして、これを5択全て計算しようとすると、時間がなくなってしまいます(汗)
そしてもう1つ。「紛らわしい」=「引っ掛け」的な要素が強いです。
例えば、問題に「右肩上がりのグラフ」が載っていて、「今年度は、前の年度よりも数量が増加している。○か×か?」みたいな問題があります。
グラフをパッと見ると、右肩上がりなので増加しているように見える。が、よく見ると、縦軸が数量ではなく、%(割合)になっている。
もし、「お寿司全体における、マグロの販売割合が40%→50%になった!」という部分だけを見ると、マグロは増加しているように見えます。が、お寿司の全体販売量が…
- 前年度=200個
- 今年度=100個
であれば、マグロの販売「数量」は…
- 前年度=200個×40%=80個
- 今年度=100個×50%=50個
となり「数量」は減少している。縦軸が%だと右肩上がりだけれども、縦軸を個数に直すと右肩下がりになります。
「何を聞かれているのか」「グラフなどの数値や表示はどうなっているのか」をしっかりと意識しながら問題を解かないと、グラフなどのビジュアルに騙される可能性があります。
資料解釈の「面倒」且つ「紛らわしい」問題への対策
では、これら「面倒」「紛らわしい」への対策について。
計算の「面倒」臭さ関しては、とにかく計算スピードを上げる。「畑中敦子の資料解釈の最前線!」の巻末では、効率の良い計算方法が紹介されていますので、それを暗記するのも1つの手です。
ひっかけ要素の「紛らわしさ」に関しては、問題演習をして、問題を解く上で注意するポイントを覚えることです。
私の場合、計算の「面倒」さに関しては諦めました。計算方法も覚えていません。
たった1問の出題のために、計算方法を暗記する時間はもったいなかったので(笑)
そして、「紛らわしさ」に関しては、問題集を1周したら、ある程度、引っ掛けポイントを見極める視点が身につきました。
この資料解釈という科目で私が感じたのは、「資料解釈を確実に得点しよう!」と考えて勉強を行うほどのものではない、ということです。
対策しなくてもかなり得点できますし、対策しても時間に対する利益が少なすぎると感じますからね。