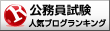公務員試験の専門科目「政治学」と「行政学」の独学による勉強方法について紹介します。
政治学と行政学は、地方上級試験では出題数はそれほど多くないものの、教養科目の「政治経済」、専門科目の「憲法」など、いろいろな科目と内容が重複しているので、それなりに勉強しておくと良いかと思います。
計算問題はなく完全な暗記科目ですが、政治や行政のしくみを知る事ができ、勉強していてなかなか面白い科目です。
「政治学、行政学」の勉強で使用した勉強教材
私が使っていた教材は以下のものです。
- 「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 政治学
」
- 「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 行政学
」
- 「公務員試験 行政5科目まるごとパスワード neo
」
- 「公務員試験 行政5科目まるごとインストール neo
」
「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 政治学」は政治学の、「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 行政学
」は行政学の問題集です。様々な公務員試験の過去問を集めた、5択の本番形式の問題集で、本番レベルの問題練習ができます。
各単元の最初には、その内容の重要ポイントがまとめられた要点整理がありますし、各単元ごとに国家2種、国税専門官、地方上級、国家1種の頻出度が★マークで表示されていますので、どの単元を重点的に勉強すればよいか分かりやすいです。
内容は政治学の方が7章30単元、行政学の方は5章20単元です。問題は基本問題と応用問題から構成されており、全て本番と同じ5択の選択形式問題です。
基本と応用それぞれ4~5問ずつくらいの問題がありますから、問題量も十分だと思います。また、問題の解説も詳しくて分かりやすいです。
国家公務員の試験にも対応しているため、地方公務員を受験する人にとっては必要ない単元も多く、十分な問題演習ができる内容だと思います。
「公務員試験 行政5科目まるごとパスワード neo」は、政治学、行政学、社会政策、社会学、国際関係の行政5科目の要点がまとめられた参考書です。
内容は、各科目の重要点を簡単にまとめたものとなっています。
そして、例えば政治学のところであれば、「政治制度」とか「選挙制度」というように、大まかな区分けがされており、その内容に関する知識がまとめて書いてあるので、知識を整理するうえでとても役立ちます。
また、頻出レベルごとに「よく出る」「出ている」「出るかも」という3段階に分けてあるという点も、的を絞って勉強するのに役立つと思います。手帳サイズというのも、気軽に持ち運べて良いです。
内容がコンパクトにまとめられているため、十分な解説とは言えず、これ1冊で十分な知識を付けるのは難しいと思います。
しかし、上記で紹介した問題集と一緒に使うことで、十分な知識を身につけることができたと思います
「公務員試験 行政5科目まるごとインストール neo」は「公務員試験 行政5科目まるごとパスワード neo
」に対応した手帳サイズの問題集です。
内容は、まず科目ごとの最初に、ウォームアップテストとして穴埋め問題が16~32問あります。次に、各科目の単元ごとに、解き方を解説している問題が1問ずつあります。そして、各科目の単元ごとに1問1答タイプの問題が8~16問と2択タイプの問題が4問程度あります。
本番に対応したような、しっかりした問題はありませんが、手早く勉強知識を確認するには便利です。
「政治学」「行政学」の勉強の進め方
私は、行政学と政治学について、「必ず得点したい科目」には位置付けていませんでしたが、それなりに得点源として考えていました。(詳しくは「公務員試験の勉強科目の絞り込み」を参照)そのため、ある程度はしっかりと勉強しておくつもりで計画をたて、取り組みました。
まず最初、ざっと問題集に目を通した際、ミクロやマクロ経済学、行政法や民法のように複雑な理論を理解するものではないと感じたので、事前に解説書などは読まず、問題演習から勉強をスタートしました。
問題演習では「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 政治学」「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 行政学
」を使いました。
そして、人物と理論を対応させるために「公務員試験 行政5科目まるごとパスワード neo」を補助として使い、覚えた方が良い内容などは「暗記ノート」にまとめます。
解く問題は基本問題のみです。ただ、全ての単元を勉強するわけではありませんでした。
「政治学」では「日本の政治思想」「戦前の欧米政治史」「戦後の欧米政治史」「戦前の日本政治史」「戦後の日本政治史」の単元には全く手をつけていません。
また「行政学」では「行政の歴史と制度」「行政学の歴史」「行政学の理論家」の単元には、ほとんど手をつけていません。
これらの単元は、地方上級試験では頻出レベルが低いです。
「必ず得点したい科目」ではない政治学と行政学で、これらの単元を勉強するのは効率が悪いと考えたため、手をつけませんでした。
上記の問題演習を「繰り返し勉強法」の時期に行いました。
次に「全科目勉強法」の時期も、「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 政治学」「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 行政学
」を使って問題演習します。
ただ、応用問題には全く手をつけませんでした。ひたすら基本問題のみを解いて、人物と理論とその特徴を暗記することを心がけていました。
そして「1科目集中勉強法」の時期は、「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 政治学」「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 行政学
」を使うとボリュームが多すぎるので「過去問500」を使うようにしました。
そして、「過去問500」の政治学と行政学の問題を解き、知識が混乱している分野を抽出してノートにまとめていきます。
特に、同じような理論を提唱している人などが混乱していたので、区別するためにノートにまとめを書いていきました。
最後に「過去問+苦手克服勉強法」の時期、私は週末の土日に「過去問500」を使って財政学の問題を全て解いて、間違ったところ、知識が曖昧なところ、苦手と感じるところを紙に書き出します。
そして、それ以外の曜日に、書き出した分野の問題演習を「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 政治学」「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 行政学
」を使って行うようにしました。
「政治学」「行政学」の勉強で難しく感じた点
政治学、行政学は、完全な暗記科目です。そして、言葉では非常に表現しにくいですが、「かなり細切れな暗記」という感じがします。
例えば、行政学や民法などは、全体に共通に使える知識があるように感じました。
民法であれば「弱者(未成年など)はしっかりと守られていて、悪(騙したり、瑕疵があったり…)は救済されない」という考えが軸にあって、そこから選択肢を論理的に考えて正誤を導く、という具合です。
しかし、政治学や行政学は違う感じがします。
ラズウェルさん=実体説
ウェーバーさん=3つの正統性
マキャヴェリさん=君主論
ラスキさん=多元的国家論
ホッブズさん=社会契約論
トルーマンさん=重複メンバーシップ
などなど。
もちろん、ラズウェルの実体説⇔ダールの関係説、ホッブズとロックとルソーそれぞれの社会契約説という具合に、互いに関係性があるものもたくさんあります。
しかし、基本的に、そのまとまりが小さく、軸となる共通知識などが無いです。
印象としては、羅列されている知識を「単純に暗記」していく感じです。論理的に考えるのではなく、「覚えていたら解ける」=「覚えていなければサッパリ分からない」という科目でした。
私は、この単純暗記作業が非常に苦手だったので、けっこう苦労しました。暗記カードを作ってみたり、まとめノートに関係図を書いてみたり…。参考書などを眺めていても頭に入らないタイプなので、とにかく手を使って覚えました。
他にも、ふと「ファイナーとフリードリヒの主張理論で、ファイナーって何を主張していたんだっけ?」と頭に浮かんできたら、面倒臭がらずにノートや参考書を開いて、毎回確認していました。
あとは、「ミランダの小腸(象徴)、小せえ(知性)クレデンダ」というように、自分が覚えやすいようにゴロを工夫してみたり。
地道な作業ですけれど、暗記は、見て、思い出す回数に比例して、知識が定着すると思いますからね。
逆に言えば、覚え始めたら簡単に解けるので楽しいです♪
「政治学」「行政学」の勉強で重要だと感じた点
もし、国家公務員Ⅱ種などを受験し、政治学、行政学を選択しようと考えているのであれば、「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 政治学」「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 行政学
」の問題集をしっかりと勉強しておく必要があると思います。
しかし、地方上級試験をターゲットにしている場合、全国型で、政治学と行政学の出題数は2問ずつです。それほど多くはありません。
そのため、上記の問題集の全てを完璧に勉強するのではなく、ある程度分野を絞って勉強すると良いと感じます。
例えば政治学の場合、「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 政治学」で地方上級の頻出レベルに★マークがついているのは30単元中、12単元のみ。
そして行政学の場合、「公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 行政学」で地方上級レベルに★マークがついているのは20単元中、15単元。ただし、その15単元のうち9単元が、★マーク1つと、それほど頻出ではありません。
私はこの情報を参考にし、あまり深い内容まで踏み込まないように心がけ、基礎問題、重要事項に重点を置いて、メリハリをつけて勉強していました。(勉強方法は上記<私の勉強の進め方>を参照してください)
当然、全ての単元をしっかりと勉強しておくことが理想ですが、それは、時間の都合上ムリです。そして、出題数から考えても、かなりムダが多いです。
「必ず得点したい科目」でない場合、出題見込みが低い内容は切り捨てて、その分、「必ず得点したい科目」を勉強するように心がけると良いと思います。