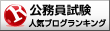自治体研究は、自分の自治体に関する「思考」をレベルアップさせる上で、とても重要になってきます。(思考?という方は、「面接対策2|公務員試験の面接対策は何をするのか」の記事をどうぞ)
ただ、自治体研究の具体的な方法については、「自治体研究:基本情報」などで詳しく書いていますので、そちらを参照して頂ければと思います。
ここでは、「自治体研究をどのように面接試験につなげていくか」、言い換えれば、「面接試験のために、どのような視点で自治体研究を行っていくか」について、私の考えを少し書いてみようと思います。
面接官(採用者)視点で考えてみる
まず最初に、面接官(採用者)の気持ちについて、私なりの考えを書いてみようと思います。
関係のない話だと思われるかもしれませんが、最終的には「面接試験に対応した自治体研究」につながってますので、気長に読んでみてください。
面接官が採用したい人間とは
さて、面接官(採用者)って、どんな人間を採用したいと思うでしょうか?
仕事ができる人間?
行動力のある人間?
素晴らしい考えを持っている人間?
どれも正解。まぁ、採用側の状況によってその要求は変わると思いますけど。でも、状況に関わらず、もっと率直に「こんな人が欲しい!」っていう人間があると思うんですよね。
それは、どんな人か?
「発展させることができる人間」
間違いなくコレです。
企業なら、その企業を「発展させることができる人間」。
自治体なら、その地域を「発展させることができる人間」。
採用側は、能力としては「行動力」でも「発想力」でも「業務処理能力」でも何でもいいので、自分の企業や地域を成長させてくれる「発展させることができる人間」が欲しいはずです。
少なくとも私が採用側なら、能力は何でもいいので、確実に自分の企業や地域を「発展させることができる」人材が欲しいです。
だって、能力があったって、自分の企業などを発展させられなければ利益を生みませんからね。
逆に言えば、発展させることさえできれば、どんな能力があろうと、利益を生み出します。
ここで、ちょっと考えてみてください。
能力は「行動力」でも「発想力」でも「業務処理能力」でも何でも良いから「発展させることができる人間」が採用側は欲しいはず、と言いました。
でも、「発展させることができる人間」ってナニ?
どんな人間?
自治体を発展させることができる人とは
では、「発展させることができる人間」ってどんな人間か、私の考えを書いてみますね。
上記では「能力は何でもいいので…」と言いましたが、私の個人的な意見として、「発展させることができる人間」には、ある共通した能力があると思っています。
それは…
「現状分析能力」
物事をより良い方向に導いていく、つまり「発展」させるためには、単なる思いつきや行動だけでは非常に難しいです。なぜなら、単なる思いつきや行動だけでは的外れの可能性があるから。
的外れなことをいくら実行しても、空回りするだけで、物事をより良い方向に導くことはできません。
現状を分析して、初めて何が必要なのかが分かります。その結果、「やるべきこと」が見えてくるんです。
- 現状を分析
- やるべき事が明確化
- 実行
- 発展!
つまり、「現状分析能力」というのは、物事をより良い方向に導くため(=発展させるため)に、最も基本となるものであり、最も重要な能力です。
私自身も仕事をする中で、「現状分析能力」の重要性を強く感じました。
事業が悪い状況に陥ったとき。新しいことを始めようとするとき。まずやることは現状の分析です。
- 自分たちの余力はどのくらいか?
- 市場はどうなっているのか?
- 現在、どんな結果が出ているのか?
- 問題点はどこか?
これらのことについて、的確に分析することで、次に何をするべきか、何ができるかが見えてきます。現状を分析するというのは、当たり前のことなんですが、本当に大切なことです。
この「現状分析能力」を持っている人間が、「発展させることができる人間」だと思います。
面接試験における自治体に関する質問
ここまでの話をふまえて、公務員試験の面接試験における「自治体に関する質問」の質問例を見てみてください。
- 「自治体(県)の活動や政策で気になることは何ですか?」
- 「自治体(県)に足りないことは何ですか?」
- 「自治体(県)の問題点は何ですか?」
- 「自治体(県)を活性化させるためにはどうすれば良いですか?」
- 「自治体(県)をPRして下さい。」
- 「自治体(県)の魅力は何ですか?」
これらの質問は、私が回答を準備していた質問や実際に面接試験で聞かれた質問ですが、これを見て「アレ?」と気がつくことがあるはずです。
これらの質問を一言でまとめると…
「あなたが分析している自治体の現状、教えてください」
となるんじゃないでしょうか。
面接試験における自治体に関係する質問の意図が、見えてきましたね。
つまり、面接試験において自治体に関係する質問をすることで、面接官が何を知りたいのかというと…
×「自治体のことについて、どれだけ調べているか?」
○「自治体の現状を、どのように分析しているか?」
だと私は思います。
これは受験者の「現状分析能力」を見てますよね。そして、これによって受験者が「自治体を発展させることができる人間」かどうかを判断していると思います。
ということは、自治体研究をする場合…
自治体研究として闇雲に自治体について調べて「ほら!こんなに調べましたよ!エッヘン!」ではなく、「現状はどうなっているか?」という視点で、筋道を立てて自治体研究を行っていく必要があるということです。
面接対策として自治体研究をする方法
上記で、「現状はどうなっているか?という視点で、筋道を立てて自治体研究を行っていく必要がある」と言いました。
ここが、面接試験に対応した自治体研究の方法で、もっとも重要な部分です。
「筋道を立てて自治体研究を行う」ということについて、もう少し詳しく説明してみますね。
面接対策としての自治体研究は「現状分析」に該当します。
では、自治体の「現状分析」として、何に着目したら良いのかというと…
- 特徴や特色
- 活動や政策
- 長所
- 短所
つまり…
- 自治体(のある地域)って、どんな特徴がある?
- 自治体(のある地域)で、どんな活動してる?
- 自治体(のある地域)の長所って何?
- 自治体(のある地域)の短所って何?
ということについて着目して分析すればいいと思います。なんだか、自己分析に似ていますよね。
そして、これらの項目を筋道立ててみると…
- 自治体には、こんな特徴がある!
- この特徴を活かして、こんな活動をしている!
- それによって、こんな効果が得られてる(こんな長所がある)!
- しかし、この短所をもっと改善する必要がある!
このように考えながら自治体研究をしてみると、単なる断片的な知識の暗記ではなく、自治体の現状が見えてきます。
これで、上記で挙げた質問例に答えることができるようになります。また、筋道立てて考えることによって自分の中に軸ができるので、少し突っ込んで質問されても、対応できるようになります。
自治体の現状分析で気を付けること
現状を分析する際、自治体の産業や雇用や社会保障etcといった、全ての分野について分析する事は不可能です。そのため、完璧を求めるのはやめた方が良いです。
全般的な情報を知っておくのは必要ですが、上記の項目などまで細かく分析するものは、自分の興味がある分野や、自分が面接で答える内容に関係する分野に絞ると良いと思います。(例えば「志望動機」や「やりたい仕事」に関連する分野など)
面接官は、面接の中で受験者が答えた分野について、「じゃあ、その分野について、どれくらい現状を知ってるんだ?」「どのように分析してるんだ?」という考えで質問をしてきます。
そのため、自分が面接で答える内容などから、質問されそうな分野を予測して対策しておけば、無駄なく自治体研究ができます。
それと、もう1つ注意点があります。
自治体の現状分析をする場合、その考察に正解は無いです。
個々の人間によって、現状をどう捉えるかは異なりますし、それに対する考えも異なります。
そのため、「コレだ!」という正解は無いです。
なので、この自治体研究では、自分なりの考えによって、現状を分析すれば良いと思います。
- 自治体の現状について、私は~と分析する
- その結果、私は~と考える!~と思う!
重要なのは「自分なりの考えを持って判断できるかどうか」。
自分なりに考えを持っているということは、受動的な人間ではなく、能動的に行動できる人間というのをアピールできますからね。
的外れなことを言ってしまったらどうしようと心配せず、自分の考えで自治体研究をして、意見を述べれば良いと思います。
自治体関係の超難問な質問
さて、ここまで長々と話をしてきましたが、もう1つだけ書かせて頂きます。
それは、面接試験における自治体に関する質問の中で、私が思いつく最も難しい質問について。
「何か良いアイディアはありますか?」
私は、この質問が一番難しいと思います。
自治体を発展させるために…
産業を活性化するために…
医療を充実させるために…
観光を盛り上げるために…
「何か良いアイディアはありますか?」
志望動機などで…
「私は自治体を発展させたいです!」
「私は産業を盛り上げたいです!」
と答えた場合、意地悪な面接官だと…
「じゃあ、具体的には何かアイディアありますか?」
これは難問です。現役の職員ですら何人が答えられるんでしょうか。
アイディアを持っている人なら大丈夫ですが、アイディアが無い人にとっては、「答えられない!」と恐くなってしまう質問ですね。
でも、そんなに恐がらなくても大丈夫ではないかと思います。私が思うに、これも「現状分析」の質問の延長じゃないかと思うんです。
私が対応した方法
実際に、私はこの質問をされました。
「自治体を発展させるために、何か具体的なアイディアはありますか?」
でも、私は自治体を発展させるアイディアを持っていませんでした。で、どうしたかというと…
「すみません。まだ考えが未熟なもので、具体的なアイディアというのは持っておりません。」
と、素直に「降参」って、そんな訳ありません。その後に付け加えて…
「ただ、当自治体は○○という特徴があります。また△△という部分を見ても、××という特徴があります。これらを活かす事によって、自治体を発展させる事ができるのではないかと思っています。」
このように答えました。
これは、別に具体的なアイディアを述べている訳ではなく、単に自分が自治体研究で分析した内容を述べてるだけですよねw
でも、面接官は「ふむふむ!」と、とっても頷いていましたよ。
アイディアというものは、簡単に出てくるものではありません。アイディアが閃くかどうかは、ほとんど運ですからね。
だからこそ、アイディアを答えるのは難しいんです。
でも、アイディアが生まれるまでには、共通の段階があります。
それが「現状分析」。
- 現状を分析
- 現状から考えると、こんなことができるかも!(=アイディア)
「現状分析」をしたからといって、アイディアが生まれるとは限りませんが、「現状分析」をしなければ、アイディアは生まれようがありません。
つまり、「現状分析」はアイディアを生むベースとなるものです。
「具体的なアイディアはありますか?」
この質問は、言葉の通りに考えると具体的なアイディアを聞いている質問ですが、もっと広い視野で捉えると、アイディアを生むベースとなる「現状分析」についても聞いている質問と考えられます。
アイディアが閃くかは運次第ですが、「現状分析」は誰にでもできることです。ということは、この質問は誰にでも答えられる質問ということになります。
そう考えると、この難問も恐がる必要はありませんよね。