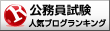ここでは、集団討論試験の当日に私がやっていたことについて書いてみます。
待合室でコミュニケーション
まず私がやっていたことは、討論試験が始まる前に、ある程度コミュニケーションをとっておくということです。
集団討論試験の当日は、まず最初に待合室で待機するところから始まります。
その際、一緒に討論するメンバーと顔を合わせる事になりますから、もし多少の会話が可能であれば、あらかじめコミュニケーションをとっておくようにしました。
これには私なりに幾つかの理由があります。
- 緊張をほぐす
- メンバーのタイプを知る
- 事前打ち合わせをする
「1.緊張をほぐす」について
待合室で待っている時点では、互いにかなり緊張しています。
そして何より空気が重く、心地悪い。全員、笑顔すら無い(笑)
そんな状態で討論がスタートしてしまうと、ガチガチ緊張状態でなかなか上手く話し合えないと思います。
最初の第一声を発するのはかなりパワーが必要ですが、少しでもコミュニケーションできると、驚くほど緊張がほぐれ、メンバー間にあった見えない壁みたいなものが消えます。
そして、討論試験に臨む上で、精神状態をベストコンディションにすることができます。
「2.メンバーのタイプを知る」について
待合室でコミュニケーションをすることで、討論メンバーの人柄を把握する事ができます。
人柄に関しては、待合室に入るとき、「失礼します!」と言ってメンバーの顔を見るだけでも、ある程度把握できますが、コミュニケーションをするとより一層把握できます。
「おとなしい」「元気」「よく喋る」「不思議系」「リーダータイプ」などなど、会話の中で様々な印象を受けますが、私が意識して確認していたのは「リーダータイプ」がいるかどうかという点です。
討論をする上で重要な役は、司会です。
司会という役回りを作らない場合でも、誰かが討論の進行を仕切らないといけないです。
もし自分の討論メンバーの中に「リーダータイプ」がいないように感じた場合は、自分が仕切りをやるつもりで、心構えをしていました。
ぶっつけ本番で、討論が始まってから「誰か司会やらないかな~」と互いに様子を伺うのもアリですが、事前にメンバーの人柄を把握できると、自分の役回りについて待ち時間にシュミレーションできるので、かなり気持ちに余裕ができます。
「3.事前打ち合わせをする」について
これは「係員がいない」「かなり雑談できる雰囲気」「順調にコミュニケーションできている」という条件が整うならばやっておく価値はあると思います。
厳密に役回りを決めておくのもありですが、「司会どうする?」とか「最後の結論発表やる?」とか、その程度の確認でも十分価値はあります。
互いの考えを確認して統一させておくだけで、討論が始まった後にバタバタ、ゴチャゴチャしなくて済みます。
討論が始まって、その場でいきなり役回りを決めるより、事前打ち合わせして、役回りや進行方法などの事務的なことを意思疎通しておけば、メンバー全員の気持ちに余裕ができます。
コミュニケーションをとる方法
まず、コミュニケーションがとれる雰囲気かどうかを確認します。
雰囲気の確認
私が経験した集団討論の待合室の形式は「円卓+係員なし」「教室タイプ+待合者多い+係員あり」「教室タイプ+待合者少ない+係員あり」の3通りでした。
「円卓+係員なし」は文句なしでOKです。
「教室タイプ+待合者多い+係員あり」も、雑談している人がいたりとそれなりに賑やかだったので、問題なしです。
問題なのは「教室タイプ+待合者少ない+係員あり」のタイプ。
この時は、一人一人の席にスペースが空いており、隣や後ろの人が遠い。加えて係員がいて、会話できる雰囲気ではない。この時は素直にコミュニケーションするのを諦めました。
コミュニケーションの方法
次に、どのようにコミュニケーションを図るのかですが、人それぞれあると思いますので、ここでは私がやっていた方法を書いてみます。
- 「集団討論がある2次試験が開始されるのは、ほとんどが夏」
- 「受験者は会場まで歩いてくるので、汗をかく」
- 「省エネのために待合室のエアコンは弱め」
このような条件が、ほとんどの集団討論試験に当てはまります(笑)
そのため、最初に「今日は宜しくお願いしますね」と挨拶したあと、次の一言が、第一声としては最も効果的です。
「それにしても、この部屋、暑いですね」
この言葉を発すると私が経験する限り100%の人が「そうですね」と返してくれます。そこですかさず…
「集団討論って、もう経験されました?」
そうすると、相手は「初めてなんです」とか「予備校では模擬討論をしてましたけど」とか「1回やりましたよ」とか色々返してくれます。そうしたらトドメの言葉を…
「私、集団討論するの初めてで緊張しちゃってー!」+笑い声
バカっぽくて申し訳ないですが、これで完璧です(笑)
これで会話ができる雰囲気が完成しますので、その後は「地元の人ですか?」とか何とか話をします。
ちなみに、「もし自分の第一声に反応してくれなかったらどうしよう…」という不安は、不必要です。待合室の空気はかなり重いですが、おそらくその場にいる全員が「誰か口を開かないかなぁ」という感情をもっているように感じました。
そのため、誰かが話し始めたら、最低でも1人は反応してくれますから大丈夫です。
ただし、待合室のときでも討論がスタートしたあとでも、第一声を発して話し始めた人は、「司会をやってくれ視線」をメンバーから受けるリスクを負うことになる気がします(笑)
私は第一声を発するタイプだったので、「待合室で第一声を発した場合は、雑談の中でさりげなく他の人に司会をすすめて反応を伺う」「討論がスタートしたら、第一声はとりあえず我慢する」に気をつけていました。
討論の司会はするべきか
人によって得手不得手がありますので何ともいえませんが、私は実際に司会をやってみて「必要に迫られない限り、司会はやらない方がいい」という結論を出しました。
「必要に迫られる状況」というのは、討論メンバーが誰も司会をやろうとしないという状況です。
私は司会をやるのが嫌いではないので、このような状況だったら司会に立候補します。
しかし、基本的には司会はやらない方が良いと考えました。
その理由として、「司会をやった討論は不合格だった」「喋りたがりなので、司会をすると喋りすぎる」「他人の意見を聞きつつ進行を構成するのは、考える時間が少なすぎる」などです。
そして、司会をしない方が、考える時間が多く、客観的に討論の進行を分析でき、意見も言いやすいように感じました。
そのため、上記でも書きましたが、「討論がスタートしてからの第一声は避ける」ようにしていました。
何回か討論を経験しましたが、第一声を発した人はすでに「仕切り」を始めた状態なので、そのまま司会になる可能性が非常に高いです。
「だれか司会やりませんか~?」と聞いたところで、「既にアンタが仕切ってるじゃん」ということで、誰も立候補しない可能性が高いです。
逆に言えば、司会をしたいなら「討論がスタートしたら最初に声をあげる」ようにすれば、ほぼ完璧だと思います。
待合室での会話は大丈夫か
よく受験生向けの本などで、「試験は待合室から始まっている!」みたいなことが書かれていて、「待合室ではお喋りしない」ということが書かれています。
そのため、待合室でコミュニケーションするのはタブーに思えます。
確かに羽目をを外した雑談はダメだと思いますが、集団討論の場合は少しコミュニケーションすることでグループの雰囲気が変わりますから、メリットの方が大きいように思います。
上記<待合室でコミュニケーション>のところでも挙げましたが、緊張がほぐれたり、互いのことが把握できたりと、討論を行う上で良い作用をもたらします。
私がコミュニケーションする場合は、「自己紹介」レベルの会話に留めていましたが、とある集団討論試験の待合室では「他にどんな自治体を受験したの?」や「予備校はどこ行ってた?」など、係員の前でかなりペチャクチャ会話していました(汗)
初めから「待合室での会話はタブー」と決めつけるのではなく、雰囲気や空気を読んで、柔軟に対応すると良いと思います。
討論の議題(テーマ)が渡されたら
私は、討論の議題(テーマ)が渡されたあと、「自分の考えをまとめる」と同時に「討論の進行方法」についても考えるようにしていました。
これは、自分が司会をやるつもりがなくても、やっていました。
討論によっては「最初に1人ずつ全員が自分の考えを述べてから、討論を開始する」という形式のものがあります。
このような形式の場合、議題(テーマ)が渡されると、各自が最初に発表する考えをまとめます。
このとき、私は自分の考えをまとめると同時に「討論をどう進めるか」について考えていました。
私の体験談
ここで、私が受験した大学職員採用試験のものを例に挙げてみます。
- 議題=「入学者を増やすためには、どのような対策を行うべきか?」
- 時間=30分
以下、「討論をどう進めるか」に関する私のメモです。
討論する内容は…
入学者が減少している原因
入学者を増やす方法
↓
入学者を増やす方法を細分化して考えやすくする
入学者を増やす方法は…
- 対外的な対策=中・高校への出前授業、宣伝広告etc
- 対内的な対策=環境の整備、有名教授を集めるetc
上記をまとめると…
- 最初に入学者が減少している原因を確認(5分)
- 次に入学者を増やす方法を細分化して討論(20分)
- 最後にまとめ&発表(5分)
この様なメモで、自分なりの討論の軸をあらかじめ作っておくと、かなり討論しやすくなります。
基本的には司会の進行方法、進行軸に従って討論をしますが、もし司会の進行があやしく、討論が迷走し始めても、このメモを元に助言を加えるなどして、軌道修正(上手くいくと討論のコントロール)が可能になります。
討論の最中にすべきこと
討論の最中、私は自分の意見を考えるのとは別に、討論の流れがどうなっているのかをメモしながら討論に参加していました。
上記の「入学者を増やすためには、どのような対策を行うべきか?」の討論の場合、どのようなメモを取っていたかというと…
入学者が減少している原因について
- Aさん=~
- Bさん=~
- Cさん=~
入学者を増やす対策について
- Dさん=○○(対外的)
- Aさん=△△(対外的)
- Cさん=××(対外的)
こんな感じです。
上記のあたりまで討論が進んできたとき、もし「入学者を増やす対策として、今皆さんが言われたのは対外的な対策だと思います。それに加えて私は対内的な対策も考えられると思います。例えば~」と発言できれば良いですよね。
このように、討論の最中も、司会がどのように進めているのかを分析して、流れをつかむようにしておくと、的確な意見や、討論中盤での的確なまとめを発言する事ができると思います。
それに加えて、「討論をどう進めるか」の事前メモを活用すると、なおさら的確な発言が可能になります。
まぁ、こんなに上手くとは限りませんけどね(笑)
ちなみに、このように討論の流れを客観的に分析するためには、司会じゃないほうがやりやすいです。
司会として進行しながら、発言者の話も聞き、流れも掴み、的確な意見も述べる…。
できる人はいると思いますが、私の場合は、頭の回転速度が足りません(笑)
なので、私は司会をしない方向で集団討論に参加していました。