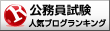ここでは、集団討論に向けての事前対策について、私が行った事を書いてみようと思います。
集団討論の過去問研究
まず私が行ったのは、受験する自治体の過去問研究です。
市町村役所などは過去問が公開されていない場合がありますが、県庁レベルだと、ホームページなどで筆記試験や小論文試験の過去問を公開していると思いますので、それで確認します。
また、予備校のホームページでも公開されている場合がありますので、それを参考にするのも良いです。
私は過去3~4年の議題(テーマ)を確認しました。
そして、過去3年に出題された議題(テーマ)に関しては、今年度は出題されないだろうと判断して、あまり勉強しないようにしました。
また、過去問研究において、1つ確認しておきたい事があります。それは、受験する自治体の集団討論の議題(テーマ)は「問題解決タイプ」「賛否タイプ」「自由討論タイプ」のどれに当てはまるかということです。
(タイプについて詳しくは「集団討論対策1|公務員試験の集団討論試験対策について」)
自治体によって「問題解決タイプ」傾向な自治体と「賛否タイプ」傾向な自治体があるように思います。自分の受験する自治体の傾向が分かれば、集団討論のイメージもしやすくなります。
時事ニュースの勉強 その1
私は、集団討論に向けての時事ニュースの勉強は、特に行いませんでした。
時事ニュースに関しては、新聞は読んでおらず、「Yahooニュース」「NHKラジオニュース」。それに加えて、小論文対策の勉強を行っており、それだけで集団討論には十分でした。
特に小論文対策として勉強する内容は、集団討論で出題されそうな議題(テーマ)と被っている内容が多いです。
そのため、小論文試験の勉強をするだけで、集団討論に応用できる良質な知識を身に付けることができます。
小論文試験の勉強には「地方上級・国家一般職[大卒]・市役所上・中級 論文試験 頻出テーマのまとめ方」を使っていましたが、この書籍は各テーマの背景、現状、問題点、解決策、事例などの情報が載っており、小論文や集団討論で出題される内容の知識を得る上でかなり使えます。
この書籍は小論文向けのため、論述の構成についても意識されており、そこがまた、討論にも応用できて便利です。
小論文を書く上で重要なのは「背景→現状→問題点→解決策」の構成。そして、討論の進め方にも同じ事が言えると思います。
この書籍で勉強しておくことで、背景、現状、問題点、解決策といった各知識が身につき、筋道立てて考える練習にもなりました。
時事ニュースの勉強 その2
もう1つ、時事ニュースの勉強として集団討論の直前に行っていたこととして、気になるニュース、出題されそうなニュースを「背景」「現状」「問題点」「解決策」「取り組み事例」に分けてまとめておくという事です。
これは、1次試験の合格発表が終わってから2次試験の集団討論や小論文が始まるまでの1ヶ月位の間に、上記で紹介した書籍では取り扱っていない内容に関して、数個行いました。
県のホームページや広報誌などを読んでいて、よく取り上げられている内容や、政策で力を入れていそうな内容だと感じたものを選んで、「背景」「現状」「問題点」「解決策」「取り組み事例」に分けてまとめておきます。
主に小論文対策として行っていたものですが、集団討論の対策にもなりました。
ちなみに、県のホームページや広報誌でよく取り上げられている内容が、集団討論や小論文で出題されるかどうかは、いまいち分かりません。
私の印象としては、出題されたりされなかったり…五分五分という印象です。
ただ、無限にある時事トピックスを闇雲に勉強するよりは、その自治体が政策で力を入れている内容などを出題してくる確立が高いかなと思い、このような方法で勉強内容を選出していました。